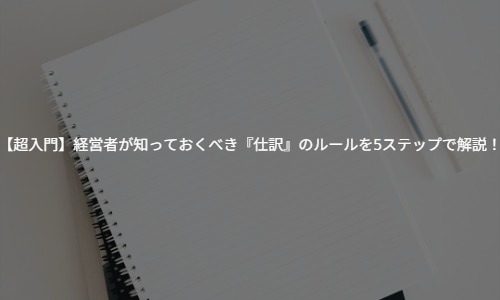「仕訳ってよく聞くけれど、実はよくわからない…」
という経営者の方は少なくありません。
仕訳を理解していないと、会計ソフトや経理担当が出した数字を正しく判断できず、
決算書や試算表を見ても「この数字は何を意味しているのか?」と迷ってしまいます。
仕訳は必ずしも社長が毎日書くものではありませんが
会計の基本として知っておけば、数字の背景がわかり、決算書の理解がぐっと深まります。
この記事では、仕訳の基本ルールをやさしく解説したいと思います。
まずは仕訳を知ることから、会計を理解する一歩を踏み出してみましょう。
仕訳ってなに?まずは基本ルールを知ろう
仕訳って何のこと?
仕訳とは、会社や事業で発生した取引を
「借方(左側)」と「貸方(右側)」に分けて記録する会計処理です。
例えば、5月1日に会社の現金でコピー用紙を500円購入した場合の仕訳はこのようになります。
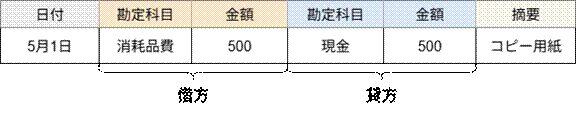
このように取引に勘定科目を決めて左(=借方)右(=貸方)に分けて記録することを仕訳といいます。
仕訳が必要な理由
財務諸表を作る基礎になる
税務署への申告書や、
関係者への情報提供に使われる損益計算書や貸借対照表といった財務諸表は、
日々の仕訳が積み重なり作られています。
日々の仕訳が正しくなければ、財務諸表全体の信頼性も崩れてしまいます。
借方貸方どっちに書く?
勘定科目は下記のように5つのグループに分けられ、
増加(発生)もしくは減少によって借方と貸方どちらに書くかきまります。
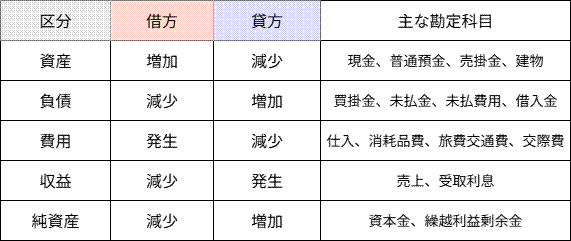
5ステップで簡単!実際に仕訳を書いてみよう!
「借方・貸方って難しそう…」と感じている方も、実際に仕訳を書いてみると案外シンプルです。
大事なのは流れを押さえて順番に整理すること。
ここでは5つのステップで詳しく解説します。
ステップ1:取引内容を確認
まずは「何があったのか」を整理するところから始めます。
ここを飛ばしていきなり仕訳を書こうとすると混乱しやすくなるので、必ず最初にやりましょう。
例1:5月1日、コピー用紙を500円現金で購入
👉「コピー用紙(モノ)を手に入れた」「現金を払った」
例2:5月2日、○○商店から売上代金1000円を現金で受け取った
👉「現金が入った」「売上が発生した」
例3:5月3日、××銀行から100万円借り入れた
👉「普通預金が増えた」「借入金が増えた」
ステップ2:勘定科目を当てはめる
次に、その取引に合う「ラベル(勘定科目)」を選びます。
勘定科目は仕訳につけるラベルのようなもの。
取引を「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」のどれに当てはめるかを決める作業です。
例1:コピー用紙を現金で購入
•コピー用紙 → 「消耗品費(費用)」
•現金で支払った → 「現金(資産)」
例2:売上代金を現金で受け取る
•受け取った現金 → 「現金(資産)」
•発生した売上 → 「売上(収益)」
例3:銀行からの借入
•入金されたお金 → 「普通預金(資産)」 •発生した負債 → 「借入金(負債)」
ステップ3:借方・貸方を決める
勘定科目を決めたら、「借方と貸方どちらに書くか」を判断します。
例1:コピー用紙購入(500円)
•消耗品費(費用)が増えた → 借方
•現金(資産)が減った → 貸方
👉 借方(消耗品費500円)/貸方(現金500円)
例2:売上代金の入金(10,000円)
•現金(資産)が増えた → 借方
•売上(収益)が増えた → 貸方
👉 借方(現金10,000円)/貸方(売上10,000円)
例3:銀行借入(1,000,000円)
•普通預金(資産)が増えた → 借方
•借入金(負債)が増えた → 貸方
👉 借方(普通預金1,000,000円)/貸方(借入金1,000,000円)
ステップ4:日付・金額・摘要を書く
仕訳は自分だけでなく、いつだれが見ても理解できるようにします。
•日付 → 取引が発生した日を正確に
•金額 → 1円単位で誤差なく
•摘要 → 「コピー用紙」「××銀行より借入」など具体的に
ステップ5:確認する
最後にチェックです。
•借方の合計金額=貸方の合計金額になっているか?
•科目の選び方は正しいか?
•摘要に内容がわかる言葉を書いたか?
などを確認しましょう。
さて、今までのステップをまとめると仕訳はこのように記入されます。
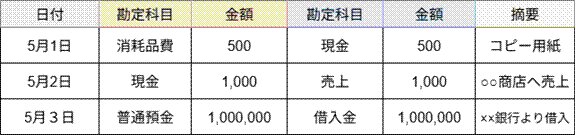
どうでしたか?
勘定科目を選んだり、借方貸方のどちらになるのかは少し慣れが必要ですが、
5ステップの流れで実際にやってみると簡単に思えてくるはずです。
まとめ
仕訳は経理担当や会計ソフトが処理してくれるものですが、
経営者にとっては「会計の基本用語」を理解するための出発点です。
仕訳を知ると、決算書や試算表の数字の背景がわかり、
銀行や税理士との会話もスムーズになるかもしれません。
渡邉一成会計事務所はクラウド会計の導入支援から日々の経理の疑問、
経営相談まで幅広くサポートしています。
「この取引ってどう仕訳すればいいの?」
「○○って会計用語について教えてほしい」などのご相談もお気軽にしていただけます。
まずはお気軽にご相談ください
サービスの内容や料金について、お客様の状況に合わせて丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です